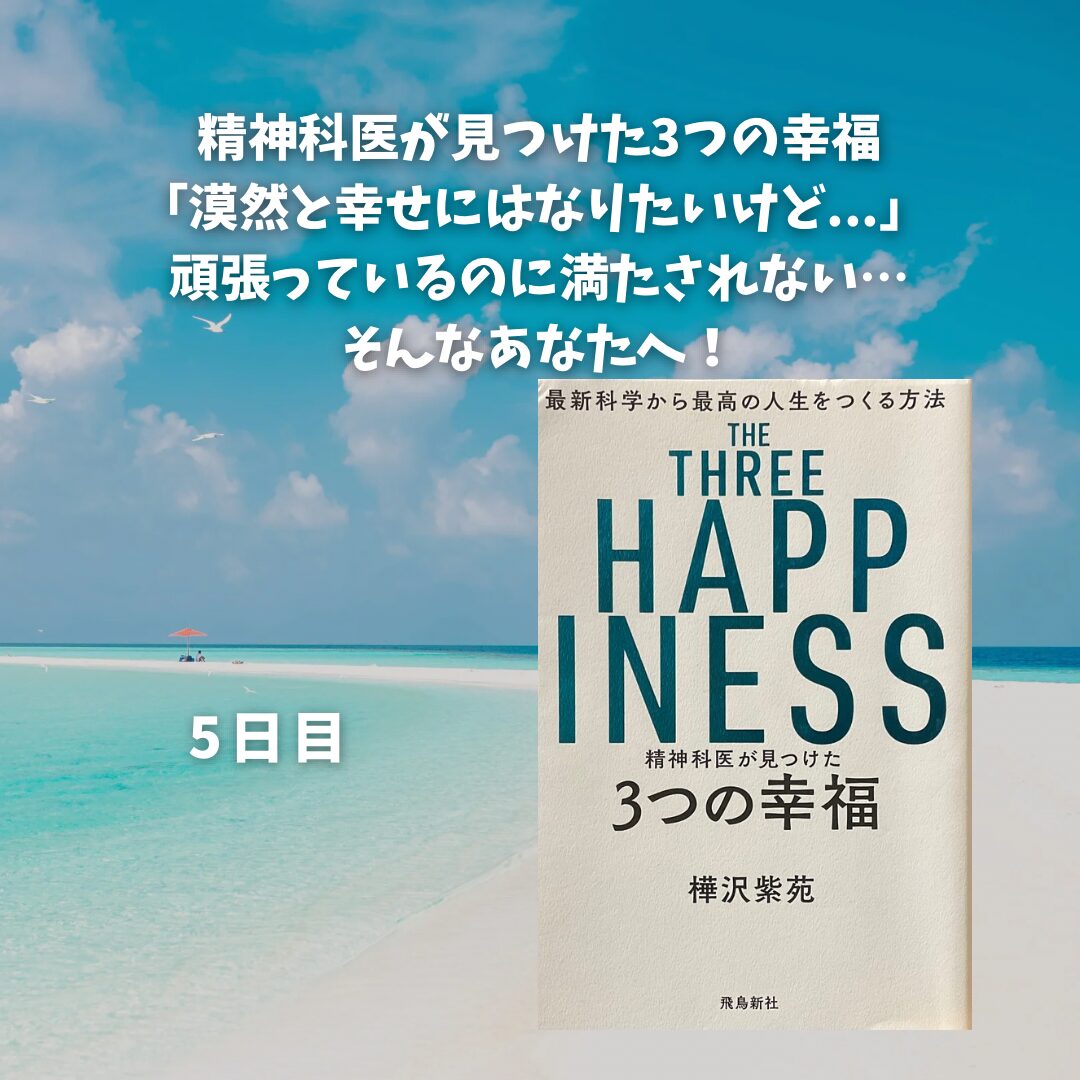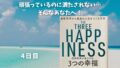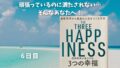著者: 樺沢紫苑タイトル: THE THREE HAPPINESS 精神科医が見つけた3つの幸福

こんな人におすすめ
- 漠然と「幸せになりたい」と思っているけれど、何をすればいいか分からない方
- 仕事や頑張りすぎで心身のバランスを崩しかけている方
- 「成功」や「お金」だけが幸せではないと感じている方
- 本当の幸福を手に入れるための具体的な方法を知りたい方
- 頑張っても報われないと感じている方
皆さん、こんにちは!
皆さんは、日々どんな時に「あー、幸せだな」と感じますか?
美味しいものを食べた時、好きな趣味に没頭している時、人との繋がりを感じる時…幸せの形は人それぞれですよね。
今回ご紹介するのは、私たちの幸福感を大きく左右する「オキシトシン的幸福」についてです。
これは、人との温かい繋がりや、穏やかな安心感から生まれる幸せのことなんです。
実はこのオキシトシン的幸福、意識的に行動することで誰でも手に入れられるもの。
この記事では、具体的な7つの方法とその実践のヒントをお伝えしていきます。
人との「つながり」でオキシトシンを分泌させる
オキシトシンは、ハグやキス、手をつなぐといったスキンシップだけでなく、アイコンタクトや会話といった心の通った交流、さらには親切な行為や感謝、そしてペットとの交流によっても分泌されると解説されています。
特に、日本人はスキンシップが苦手だと指摘しつつも、最も手軽にオキシトシンを増やす方法なんです。
また、孤独がオキシトシン不足の状態であり、健康に悪影響を及ぼす「孤毒」であると警鐘を鳴らしています。

「スキンシップが苦手な日本人」という指摘は、まさに耳が痛い話です。でも、直接的な触れ合いだけでなく、心のこもった会話や親切な行動でもオキシトシンが出るというのは、とても希望が持てますよね。
ペットを飼っていない人でも、ちょっとした親切や「ありがとう」の言葉で、自分も相手も幸せになれる、素晴らしいですよね。
孤独が「孤毒」というのは衝撃的でしたが、それだけ人との繋がりが私たちの心身にとって不可欠なんだと改めて実感しました。
「孤独」を解消する具体的な方法
孤独を解消するためには、自ら積極的に人とのつながりを構築する努力が必要だと述べられています。
具体的には、「友達は作るもの」という意識を持ち、まずは共通の目的を持つ「仲間」をコミュニティで作ることから始めることを推奨しています。
趣味のサークルや習い事など、既存のコミュニティへの参加がその第一歩。
最終的には、自分でコミュニティを立ち上げ、自分を中心に円を描くことで、気の合う仲間だけの居心地の良い空間を作ることが理想とされています。
また、オンラインでの交流が増える現代だからこそ、リアルでの交流の重要性を強調しており、SNSの効果を過信しないよう促しています。
さらに、健康や認知症予防の観点から、リタイアせずに仕事を続けることや、夢中になれる「趣味」を持つことの重要性も述べられています。

「友達はできるものではなく、作るもの」。
この言葉にはハッとさせられました。
ついつい受け身になりがちですが、やはり自分から行動しないと何も始まらないんですよね。
いきなり友達を作るのが難しくても、「仲間」から始めるというアドバイスは、内向的な私にも実践しやすそうです。
そして、「自分を中心に円を描く」という発想には、大きな可能性を感じました!
自分が本当に好きなことを軸にコミュニティを作れたら、最高の居場所になりそうですよね。
また、リアルな交流の価値が再認識されているのは、オンライン化が進む現代だからこそ、特に心に響きました。
仕事や趣味を続けることが健康や幸福に繋がるというのも、納得感がありました。
「人間関係」を良好に保つ秘訣
人間関係は自然に育つものではなく、意識的な努力が必要であると強調されています。
人間関係やコミュニケーションについて学ぶことの重要性を説き、書籍などで知識を得て実践することで改善が見込めると述べています。
さらに、時間や精神的エネルギーが有限であることを踏まえ、全ての人間関係を良好に保つのは不可能であるとし、家族、友人、職場の順で優先順位をつけ、それぞれ2~3人程度の「重要な数人」との親密な関係を深めることを提案しています。
特に、家族や友人との盤石な関係が、職場でのストレスを軽減する「癒やしの場」となると解説されています。

人間関係って、本当に難しいテーマですよね。
「努力しないと最高の人間関係は生まれない」という言葉は、耳が痛いけど真実です。
でも、コミュニケーションスキルは学べるものだというのは救いです。
そして、「みんなと仲良くしよう」とすると疲弊するというのは、まさに私の経験とも一致して、ものすごく共感しました。
「重要な数人」に絞って深く関わるという考え方は、とても現実的で、これなら無理なく人間関係を育んでいける気がします。
家族や友人が癒やしの場になるというのは、本当にその通りだと思います。
「親切」を実践し、「感謝」する習慣を身につける
オキシトシンが「親切のホルモン」とも呼ばれるように、親切な行為は親切をした人・された人の双方にオキシトシンを分泌させ、幸福度を高める効果があると解説されています。
さらに、健康効果や人間関係の改善、ドーパミン的幸福の増加にも繋がるとのこと。
意識的に親切を行う「親切ワーク」(1日3回親切をする)とその記録である「親切日記」が推奨されています。
親切を記録するだけで「自尊感情」が高まり、幸福度がアップすると説明されています。
親切に加えて「感謝」も重要で、感謝されるとオキシトシンに加え、エンドルフィン、セロトニン、ドーパミンという4つの幸福物質が全て分泌される究極の幸福状態になると述べられています。
1日3回、誰かに感謝し「ありがとう」を言葉で伝える「感謝ワーク」と、それを記録する「感謝日記」が効果的だと紹介。
特に、嫌いな人や対立している人にこそ「ありがとう」を言うことの重要性を説いています。これらを組み合わせることで、短期間で人間関係や幸福度が改善されるとのことです。

「親切」は伝染するという話にはとても納得しました。
自分が親切にすることで、相手も親切になり、結果的に周りの人間関係まで良くなるなんて、素晴らしい循環ですよね!
「親切ワーク」と「親切日記」は、最初は難しそうだけど、その分効果が大きいというのも魅力的です。
そして「感謝」の力。
「ありがとう」が究極の魔法の言葉とは、まさにその通りですね。
特に、苦手な人にこそ「ありがとう」を言うという逆転の発想は、凝り固まった人間関係を解きほぐすのに役立ちそうです。
動物や植物を「育てる」喜び
パートナーや子供がいない人でも、ペットや動物を飼うことでオキシトシン的幸福が得られると説明されています。
ペットとの交流は、オキシトシンを分泌させ、孤独感を癒し、自己重要感を高める効果があるとのこと。
ペットを飼うことで、幸福度が高まり、ストレス軽減、健康改善など、心身両面でのプラスの効果が多数報告されています。
さらに、ペットを飼えない人には、ガーデニングなど「植物を育てる」こともお勧め。
高齢者の研究では、植物の世話が幸福度を高め、死亡率を半減させたという興味深い事例も紹介されています。
これも、「相手の役に立っている」という自己重要感に繋がり、オキシトシン分泌を促すためと捉えられています。

人との直接的な交流が苦手な人でも、動物や植物との触れ合いから、これほど多くの幸福が得られるなんて!
確かに、ペットを撫でていると、なんとも言えない穏やかな気持ちになりますよね。
植物を育てることで死亡率が下がるという研究結果には、驚きました。
まさに、何かを育てるという行為が、私たちの心身に良い影響を与えてくれる証拠だと感じました。
「他人を信頼する」ことの絶大な効果
病気治療においても、主治医を信頼することが治癒を早めると解説されています。
患者が主治医を信頼するだけでオキシトシンが分泌され、免疫力向上やリラックス効果が得られるため、病気の回復を助けるとのこと。
また、「プラシボ効果」にもオキシトシンが深く関わっており、医師や薬を信じることで、薬の効果が3倍も高まる可能性があると説明されています。
さらに、アドラー心理学の「自己受容」→「他者信頼」→「他者貢献」という幸福への道筋も紹介されています。
見返りを求めずに「無条件に他人を信頼する」ことが、オキシトシン分泌を促し、幸福へと繋がるという脳科学的な裏付けがあると述べられています。

「主治医を信頼するだけで病気が治りやすくなる」という話は驚きです。
心と体の繋がりを改めて実感しますね。
そして、アドラー心理学の「無条件に他人を信頼する」という考え方が、脳科学的に正しいと示されているのは、非常に興味深いです。
人間関係で悩んだ時、まずは自分から心を開くこと、相手を信頼することが、結局は自分の幸せに繋がるんだと強く感じました。
「結婚」がもたらすオキシトシン的幸福と「試練」
結婚が一時的に人生の満足度を上げるものの、2年程度で幸福感に慣れてしまうというデータがある一方で、既婚者のほうが未婚者よりも幸福度が高いという調査結果も紹介されています。
この矛盾について、熱愛の「ドーパミン的愛情」は2~3年で減少するが、安らぎや安心感をもたらす「オキシトシン的愛情」に置き換わっていくことで、永続的な関係が築かれると解説されています。
告白やプロポーズのタイミングもドーパミンの特性から導き出しており、ピークの2~3ヶ月以内(告白)や2年以内(プロポーズ)が重要だと指摘。
結婚は「ゴール」ではなく「試練」であり、夫婦で困難を乗り越えることでオキシトシン的幸福が積み上がり、自己成長に繋がると述べられています。
「ヤマアラシのジレンマ」の概念を用いて、夫婦間の適度な距離感と、お互いの尊重、感謝の気持ちが重要だと説いています。
子育ても同様に「試練」であり、家族で協力して乗り越えることでオキシトシン的幸福が育まれると説明されています。
最終的に、セロトニン的幸福、オキシトシン的幸福、ドーパミン的幸福の「3つの幸福」を掛け合わせることで、愛と成功の両方を手に入れられる「幸せな結婚生活」が築けると結論付けています。

結婚に関する話は、まさにリアルで納得感がありました。
「ドーパミン的愛情」から「オキシトシン的愛情」への移行という考え方は、長続きする関係を築く上でとても参考になります。
そして、「結婚はゴールではなく試練」という言葉は、結婚経験者なら誰もが頷くのではないでしょうか(笑)。
でも、その「試練」を乗り越えることで、より深い愛情や自己成長が得られるというポジティブなメッセージに、勇気づけられました。
夫婦で「感謝ワーク」を行うという具体的なアドバイスも、実践しやすそうでいいですね!
本日のまとめ
今回は、私たちが日々の生活の中で感じられる「オキシトシン的幸福」を増やすための7つの方法をご紹介しました。
- 繋がりを意識する: スキンシップ、心の交流、親切、感謝、そしてペットとの触れ合いを大切にしましょう。
- 孤独を解消する: 自分から積極的に人間関係を構築し、仲間を作り、時には自分中心のコミュニティを築く勇気を持ちましょう。リアルな交流の重要性も忘れずに。
- 人間関係を整える: 全員と仲良くする必要はありません。家族、友人、職場の「重要な数人」に意識を集中し、関係を深める努力をしましょう。
- 親切と感謝の実践: 「親切ワーク&親切日記」や「感謝ワーク&感謝日記」で、意識的に親切や感謝の気持ちを行動に移し、記録することで、自己肯定感と幸福度が高まります。
- 育てる喜びを感じる: ペットや植物を育てることで、自己重要感が満たされ、オキシトシン的幸福が得られます。
- 他人を信頼する: 主治医を信頼することから始まるように、見返りを求めず無条件に他人を信頼することで、心の健康と幸福に繋がります。
- 結婚を「試練」として捉える: 結婚はゴールではなく、夫婦で協力して困難を乗り越える「試練」です。ドーパミン的愛情から オキシトシン的愛情へと移行し、互いに感謝し、尊重し合うことで、永続的な幸福を築けるでしょう。
これらの方法は、どれも日々の少しの意識と行動で始められるものばかりです。
今日からできることから、ぜひ取り入れてみてください。
きっと、あなたの人生に、より多くの「幸せ」と「癒やし」が訪れるはずです。
幸せな人生は、日々の小さな積み重ねから生まれます。あなたの行動が、明日を、そして未来をより豊かにしていくと信じています。

▼本書の詳細・購入はこちら