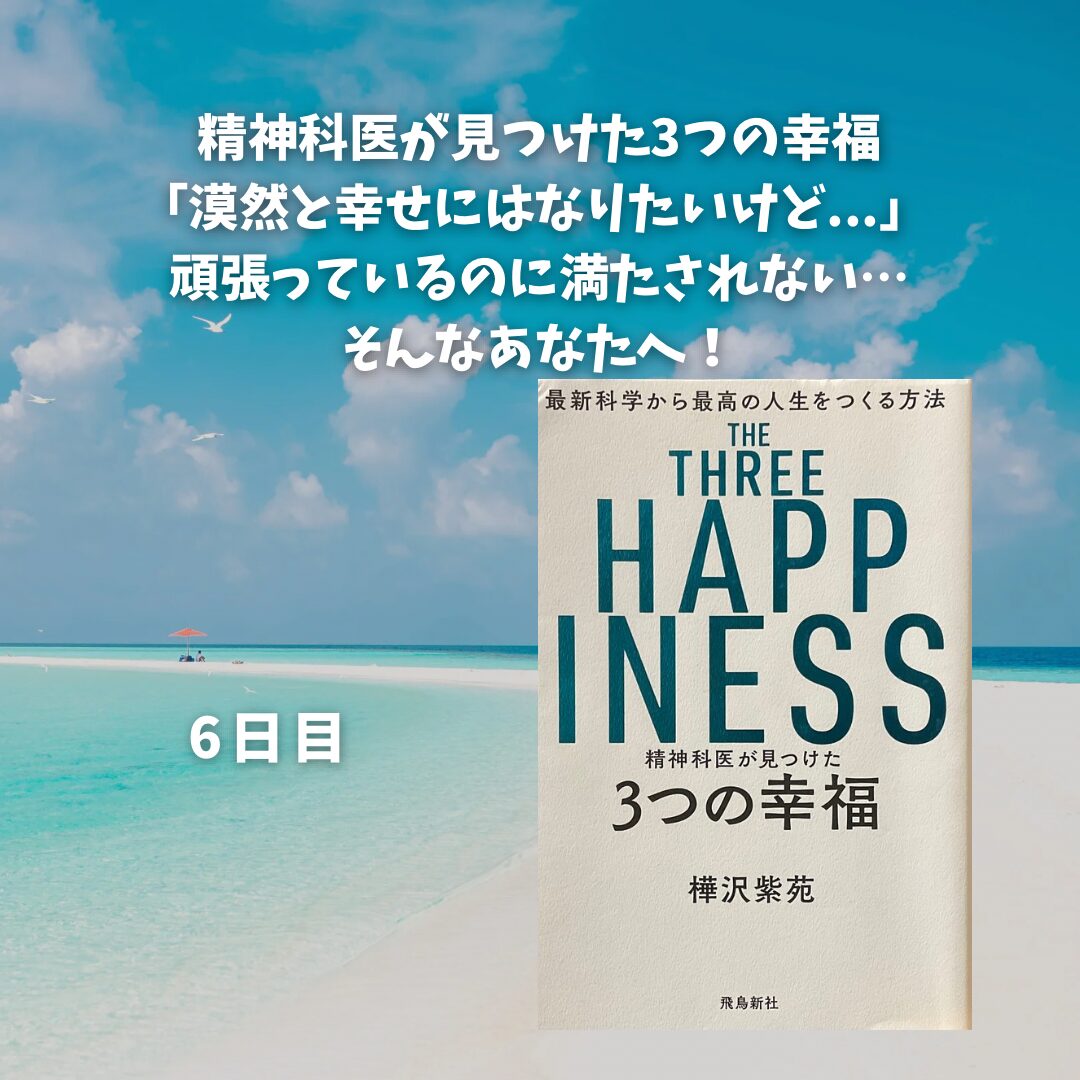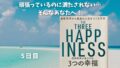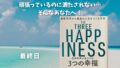著者: 樺沢紫苑タイトル: THE THREE HAPPINESS 精神科医が見つけた3つの幸福

こんな人におすすめ
- 漠然と「幸せになりたい」と思っているけれど、何をすればいいか分からない方
- 仕事や頑張りすぎで心身のバランスを崩しかけている方
- 「成功」や「お金」だけが幸せではないと感じている方
- 本当の幸福を手に入れるための具体的な方法を知りたい方
- 頑張っても報われないと感じている方
仕事の成功、お金、社会的な評価…多くの方が、「幸せ」=「ドーパミン的幸福」を思い浮かべるのではないでしょうか。
私も含め、そう答える人は少なくありません。
でも、もしその「幸せ」が、私たちの想像とは少し違う顔を持っているとしたら?
今回は、そんなドーパミンの奥深さに迫り、私たちが真に幸福を感じるためのヒントを皆さんと一緒に探求していきたいと思います。
巷で言われる「ドーパミン=幸福」という単純な図式では語れない、その「光と闇」、そして「真の幸福」を手に入れるための具体的な方法について、本書の内容を紐解きながら、私の考察も交えてお伝えしていきますね。
ドーパミンは「幸福物質」か、それとも「依存症の元凶」か?
まず、本書を読んで衝撃を受けたのは、ドーパミンが「幸福物質」としてだけでなく、「依存症の原因物質」としても広く認識されているという事実です。
かつて「幸福ホルモン」として知られていたドーパミンは、今や「依存症」と結びつけられることが多くなっています。
特に海外のサイトでは、その「闇」の側面が強調され、安易な快楽追求が依存症につながると警鐘を鳴らしているとのことです。

私も以前はドーパミンと聞くと、単純に「幸福感」や「やる気」といったポジティブなイメージしか持っていませんでした。
しかし、その裏に「依存症」という危険が潜んでいると知り、ドーパミンの両面性を深く理解することの重要性を痛感しました。
まるで諸刃の剣のようですね。
ドーパミンの「光」:自己成長と学習の原動力
しかし、ドーパミンには素晴らしい「光」の側面も存在します。
ドーパミンは「自己成長物質」であり、「学習物質」でもあります。
目標達成時の「やったー!」という達成感や、「もっと頑張ろう」という意欲、集中力、記憶力の向上など、私たちの学びや成長を加速させる働きがあるそうです。
人間が科学や文化を進化させてきたのも、このドーパミンの働きによるところが大きいと説明されています。

この部分は、まさにドーパミンが持つポジティブな側面を凝縮していると感じました。
努力して成果を出すことで得られる喜びが、さらなる成長の原動力となる。
これは、仕事や勉強だけでなく、趣味やスポーツなど、あらゆる分野で私たちが経験する「上達の喜び」そのものですよね。
ドーパミンは、私たちの可能性を広げてくれる素晴らしい存在だと改めて認識しました。
ドーパミンの「闇」:安易な快楽と依存症の罠
一方で、ドーパミンを安易に追求すると、その「闇」に囚われてしまう危険性も指摘されています。
ドーパミンは「もっともっと」を求める性質があり、努力を伴わない「楽で簡単な幸せ」に流れやすい傾向があります。
お酒、ギャンブル、買い物、ゲームなど、手軽にドーパミンが得られるものに欲望が暴走すると、アルコール依存症やギャンブル依存症といった「依存症」に陥る危険性があるとのことです。
ドーパミンを上手に使いこなせるかどうかが、人生の成功と幸福の分かれ目になると述べられています。

この「楽で簡単な幸せ」に流れやすいという話は、耳が痛い方も多いのではないでしょうか?
ついつい手軽な快楽に走ってしまいがちな現代において、誰もが陥る可能性のある罠だと感じました。
特に、スマートフォンの普及により、誰もが簡単にドーパミンを刺激できる環境にある今、この「闇」の側面を理解し、自制する力がより一層求められているのだなと強く感じました。
ドーパミン的幸福を手に入れる7つの方法
では、どのようにすればドーパミンの「光」を最大限に活かし、真の幸福を手に入れることができるのでしょうか?本書では、その具体的な方法が7つ紹介されています。
1. お金や物に「感謝する」
お金持ちになっても幸福になれないという研究結果は興味深いですね。
年収が高くても幸福度の差はわずかであり、高額宝くじ当選者の幸福感も数ヶ月で消滅するといった研究が紹介されています。
持続的な幸福を得るためには、お金や物に対して「感謝」の気持ちを持つことが重要であると述べられています。
「お金の専門家」である本田健氏やアンソニー・ロビンズ氏も、感謝の気持ちが富を引き寄せると説いているそうです。
脳科学的にも、感謝(オキシトシン的幸福)と金銭的幸福(ドーパミン的幸福)を結びつけることで、幸福感が持続すると説明されています。

この「感謝」の概念が、ドーパミン的幸福の持続に繋がるという話には非常に納得しました。
確かに、何かを手に入れた瞬間は嬉しいですが、その喜びはすぐに薄れてしまいます。
しかし、その過程で関わった人々や、その物がもたらしてくれる恩恵に感謝することで、より深く、持続的な幸福感を得られるというのは、まさに本質をついていると感じました。
ビジネスにおいても、顧客や従業員、取引先への感謝が信頼を生み、それが結果として売上や成長に繋がるという循環は、非常に理にかなっていますね。
2. 「制限する」ことでドーパミンの逓減を防ぐ
チョコレートの実験は、ドーパミンの性質をよく表しています。
ドーパミン的幸福はすぐに逓減(飽きてしまう)するため、その幸福感を長く楽しむには「制限する」ことが有効だと説かれています。
チョコレートを我慢したグループの方が、その後のチョコレートをより楽しめたという研究が紹介され、スマホ、ゲーム、お酒などのドーパミン的な娯楽も、制限することで依存症を防ぎ、長く楽しめるようになると具体例を挙げて説明されています。

「制限」という言葉を聞くと、最初はネガティブなイメージを持つかもしれません。
しかし、本書では、制限が「より長く、深く楽しむ」ためのポジティブな手段として提示されているのが新鮮でした。
私もついつい「もっと!」と求めてしまうタイプなので、意識的に制限を設けることの重要性を再認識しました。
特に、お酒やゲーム、スマホなど、日常生活に溶け込んでいるものこそ、自分なりのルールを持つことが大切だと感じました。
健康面への影響も考慮すると、まさに「賢い選択」ですね。
3. 毎日の「自己成長」を味わう
自己成長は「昨日できなかったことができるようになる」「昨日知らなかったことを知っている」という日々の小さな変化であり、私たちは毎日自己成長していると述べられています。
この「プチ成長」を意識することで、ドーパミンが分泌され、モチベーションが維持され、継続につながると説明されています。
逆に、日々の成長に気づかないとモチベーションが下がり、挫折しやすくなると指摘されています。

この「プチ成長」という考え方は、大切です!
私たちはつい大きな変化ばかりを求めてしまいがちですが、日々の小さな進歩に目を向けることの大切さを教えてくれました。
この意識を持つことで、日々の仕事や学びがもっと楽しく、充実したものになるはず!
4. 「コンフォートゾーン」から出てチャレンジする
「失敗したくない」という気持ち、誰にでもありますよね。
ドーパミン的幸福を得るには、快適な領域である「コンフォートゾーン」から出て「チャレンジ」することが最短の道だと述べられています。
ただし、いきなり無謀な挑戦をするのではなく、「ちょい難(ちょっとだけ難しい)」課題に挑むことが重要であり、それをクリアすることでドーパミンがたっぷり分泌されると説明されています。
「チャレンジが怖い」という感情は人間の本能的なものだが、脳の働きを理解し、小さなチャレンジを繰り返すことで克服できると強調されています。

「ちょい難」という言葉が、チャレンジへのハードルをぐっと下げてくれました。
私自身失敗を恐れてなかなか新しいことに踏み出せないことが多いのですが、「ちょっとだけ難しい」なら挑戦してみようかな、と思えますね。
人生をRPGに例えているのも面白く、宝物は「旅立ちの村」(コンフォートゾーン)の外にある、という表現には納得しかありませんでした。
ワクワクする気持ちを大切にし、少しずつでも行動することの重要性を学びました。
5. 「自己肯定感」を高める
「自己肯定感が低い」という悩み、多くの人が抱えているかもしれません。
自己肯定感が低い人は、自己成長やチャレンジを避けがちであると指摘されています。
自己肯定感は「心の健康(セロトニン的幸福)」と「安定した人間関係(オキシトシン的幸福)」の両方に関連しており、高めることで幸福度に直結すると説明されています。
新しい人間関係を築いたり、「ちょい難」に挑戦して小さな成功体験を積み重ねたりすることが、自己肯定感を高める具体的な方法として挙げられています。
自己肯定感が低いと依存症に陥りやすい危険性も指摘されています。

自己肯定感の低さが、ドーパミンの暴走や依存症にも繋がりやすいというのは、非常に重要な指摘だと感じました。
幸福の基盤が不安定なままだと、どんなにドーパミン的幸福を求めても、それが持続しないということですね。
成功体験を積むことだけでなく、新しい人間関係を築くことで自己肯定感が高まるというのは、まさに「人とのつながり」の重要性を示していると思います。
自分を肯定し、自信を持つことで、より豊かな人生を送れるようになるのだと改めて感じました。
6. 「与える(ギバーになる)」ことを意識する
「与える人」が成功する一方で、最も失敗するのも「与える人」という事実!
アダム・グラントの著書『GIVE&TAKE「与える人」とそ成功する時代』から、最も成功するのも失敗するのも「ギバー」であり、「自己利益」も求める「他者志向の成功するギバー」になることが重要だと説明されています。
自己犠牲的な与え方は燃え尽きにつながりやすく、長期的な視点での「与える」こと(3年続ける)が、何倍もの見返りとなって返ってくる「返報性の法則」の例として紹介されています。

「自己犠牲的なギバーは燃え尽きる」という話は、非常に現実的で心に響きました。
私も、ついつい頑張りすぎてしまう傾向があるので、無理なく「与える」ことの重要性を学びました。
特に「人助けはまとめてやる」「100時間ルール」「周囲からサポートを受ける」といった具体的な方法は、実践しやすいヒントだと感じます。
そして、「与えたものが返ってくるのに3年かかる」という言葉は、長期的な視点を持つことの大切さを教えてくれました。
焦らず、継続して与え続けることの大切さを心に留めておきたいです。
7. 「天職」を見つける
人生の多くの時間を費やす「仕事」が、幸福に直結するとのこと。
天職を見つけることが幸福につながるのは、「自己実現(ドーパミン的幸福)」と「社会貢献(オキシトシン的幸福)」が一致するからだと説明されています。
仕事には「ライスワーク(生活のため)」「ライクワーク(好きな仕事)」「ライフワーク(天職)」の3つの分類があり、天職は「楽しい」という感情を伴い、モチベーションや生産性を高めると述べられています。
天職は意外と身近なところにあり、ワークスタイルや「やること」を少し変えるだけでも見つかる可能性があると示唆されています。

「天職」というと、全く新しい分野に飛び込むようなイメージがありましたが、本書では「今の仕事の中で見つける」可能性も示唆されていて、希望が持てました。
私も、日々「何が楽しいのか」「何に興味があるのか」というアンテナを立てて、自分の「ワクワク」を大切にしていこうと思います。
仕事が楽しければ、人生全体が楽しいくなるという言葉は、まさにその通りだと感じました。
しかし理解できるものの、理想と現実のギャップに悩む人が多いのではないでしょうか?
本日のまとめ
今回は、ドーパミンがもたらす幸福と、その裏に潜む依存症のリスクについて深く掘り下げ、真の幸福を手に入れるための7つの具体的な方法を学びました。
ドーパミンは、使い方次第で私たちの人生を大きく左右する可能性を秘めた脳内物質です。
- 闇の側面に飲み込まれず、光の側面を最大限に活用するためには、意識的な「制限」が不可欠です。
- 日々の「プチ成長」に気づき、「ちょい難」なチャレンジを繰り返すことで、持続的なドーパミン的幸福を得られます。
- お金や物、そして人に対して「感謝」の気持ちを持つことで、ドーパミン的幸福はより深く、長く続くものになります。
- そして、自己肯定感を高め、「与える」ことを実践し、最終的には「天職」を見つけることで、人生全体を幸福で満たすことができるのです。
今回の学びは、私たちがより充実した人生を送るための一歩を踏み出す勇気を与えてくれました。
皆さんも今日からできる小さなことから、ぜひ実践してみてくださいね!

▼本書の詳細・購入はこちら