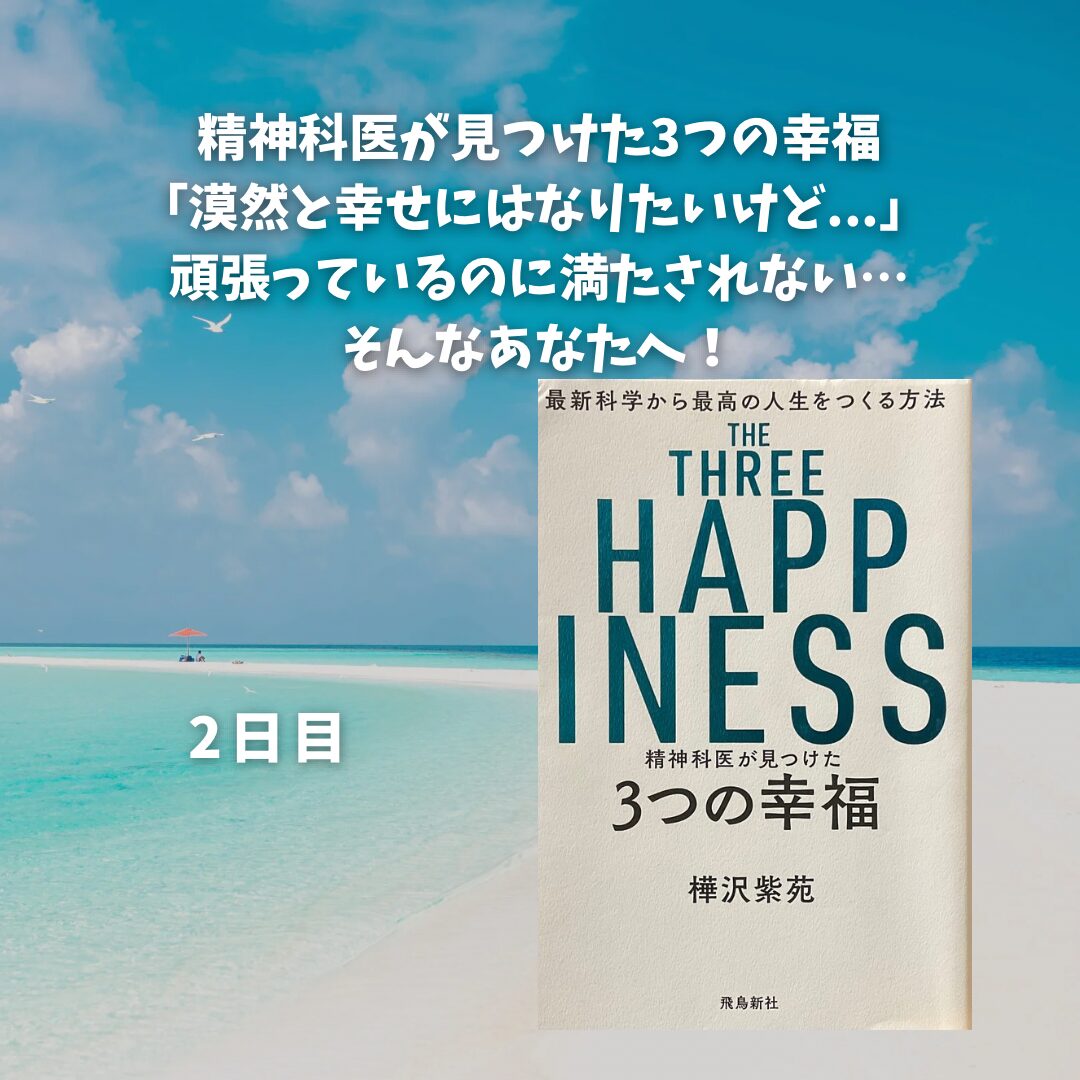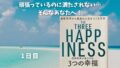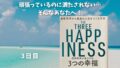著者: 樺沢紫苑タイトル: THE THREE HAPPINESS 精神科医が見つけた3つの幸福

こんな人におすすめ
- 漠然と「幸せになりたい」と思っているけれど、何をすればいいか分からない方
- 仕事や頑張りすぎで心身のバランスを崩しかけている方
- 「成功」や「お金」だけが幸せではないと感じている方
- 本当の幸福を手に入れるための具体的な方法を知りたい方
- 頑張っても報われないと感じている方
皆さん、突然ですが「幸せ」って何だと思いますか?
お金がたくさんあれば幸せ? 好きな人と一緒にいられれば幸せ? それとも、毎日健康であれば幸せでしょうか?私たちは日々の生活の中で、漠然と「幸せになりたい」と願っています。
しかし、「幸せとは何か」について深く考える機会は案外少ないものです。特に、予測不能な出来事が次々と起こる現代において、私たちの「幸せの形」もまた、変化を求められています。
今回のブログでは、書籍『精神科医が見つけた3つの幸福』の中から「3つの幸福」という概念と、その重要性についてご紹介します。
この「幸せの三段重理論」を知ることで、きっとあなたの「幸せ」に対する考え方が変わるはずです。
この章では、「幸せの三段重理論」を構成する3つの幸福、つまり「セロトニン的幸福」「オキシトシン的幸福」「ドーパミン的幸福」について、それぞれがどのような状態を指し、どのような感情を伴うのかが詳しく説明されています。
また、それぞれの幸福が失われたときに何が起こるのか、そして、それらがどのように関連し合っているのかについても深く掘り下げられています。
セロトニン的幸福:「健康」と「心の安定」が土台
著者はまず、セロトニン的幸福を「心と体の健康」と定義しています。
これは、「体調が良い」「気分が良い」「清々しい」「爽やか」といった感覚で、私たちが普段当たり前だと思っている「健康」そのものです。
朝の散歩で感じる清々しさ、運動後の爽快感、座禅を組んでいるときの平静な心などがこれに当たります。
一方で、セロトニンが低下すると、気分が沈んだり、イライラしやすくなったり、不安に襲われたり、集中力が低下したりすると警告しています。
うつ病は究極的なセロトニン低下の状態であり、体の痛みを感じやすくなることも指摘されています。
そして何よりも、「健康」は失って初めてそのかけがえのなさに気づく、非常に重要な幸福であると強調されています。

これまで、健康であること自体を「幸せ」と意識することはあまりありませんでした。若い時はあまり気にしないですよね。
どちらかというと、健康は「当たり前」の前提で、その上で何かを達成することや、誰かと楽しく過ごすことこそが「幸せ」だと思っていたんです。
でも、考えてみれば、風邪を引いたり、どこか体が痛くなったりするだけで、途端に日々の活動が制限され、気分も沈んでしまいますよね。
特に心に残ったのは、「当たり前だから気づかない」という言葉です。
朝気持ちよく目覚める、食欲がある、自分の足で歩ける…これらが当たり前すぎて、その幸福に感謝することすらしていなかったと反省しました。予防の重要性も強く訴えられていますが、本当にその通りで、失う前にケアすることの大切さを改めて気づかせてもらいました。
オキシトシン的幸福:「つながり」がもたらす安心感
次に、オキシトシン的幸福は「つながり」の幸福、つまり他者との関係によって生まれる幸福全般を指します。
家族、友人、恋人、職場の同僚など、大切な人との交流から生まれる「楽しい」「嬉しい」「安らぐ」「満たされる」といった感情がこれに当たります。
誰かと一緒にいるときの安心感や癒やし、コミュニティに所属することによる帰属意識もオキシトシン的幸福に含まれます。
逆に、この幸福が失われると、「孤独」や「孤立」を感じ、寂しさや疎外感につながると述べています。
人間関係のストレスがメンタル疾患を引き起こし、セロトニン的幸福まで失われる連鎖反応が起きる可能性も示唆しています。
職場での人間関係が仕事の生産性にも大きく影響し、ドーパミン的幸福の実現にはオキシトシン的幸福が不可欠であると強調されています。

「つながり」の幸福が、これほどまでに私たちの生活に深く根ざしていることに改めて気づかされました。
私自身、ここ最近周りとの関わりを意識的に増やすようにしてはいますが、少し人と話すことが心の平穏に繋がっている実感がもてます。
まさに、このオキシトシン的幸福を享受しているからなんだと納得できました。
仕事でも、人間関係の良し悪しがモチベーションに直結すると感じることが多々あります。
特に、孤独が心身の健康を蝕むという指摘には、現代社会が抱える問題の本質が凝縮されているように感じました。
オンラインでのつながりも増えましたが、やはり対面での温かい交流は、心の安定に不可欠なのだと改めて認識しました。
ドーパミン的幸福:「成功」と「達成」がもたらす高揚感
そして、三段重の最上段に位置するのがドーパミン的幸福で、これは「成功」や「達成」によって得られる高揚感を伴う幸福です。
お金を得る、欲しいものを手に入れる、昇進・昇給、人からの評価など、目標を達成したときの喜びや楽しさがこれに該当します。
ドーパミンは「もっともっと」という意欲の源であり、自己成長を促す原動力にもなります。ゲームや趣味、娯楽から得られる「楽しい」「面白い」という感覚もドーパミン的幸福の一部です。
しかし、著者はドーパミンの「暴走」に警鐘を鳴らしています。
アルコール、薬物、ギャンブル、買い物、ゲーム、スマホなど、手軽にドーパミンを得られる「快楽」に溺れると依存症になり、自己破綻を招くリスクがあると警告しています。
依存症になると、セロトニン的幸福やオキシトシン的幸福までも失い、人生が破綻する可能性を示唆しています。

ドーパミン的幸福は、最も分かりやすく、多くの人が追い求めている幸福の形だと感じました。
「成功したい」「認められたい」という気持ちは、誰もが持っているものではないでしょうか。
私も、目標を達成したときの喜びや、新しいスキルを習得できたときの達成感は、何物にも代えがたい「幸せ」だと感じます。
一方で、ドーパミンの「底なし沼」という表現にはハッとさせられました。
手軽に得られる快楽に依存することで、かえって人生を台無しにしてしまうという現実は、SNSの普及や情報過多の現代において、特に意識すべきことだと感じます。
例えば、私もSNSを見ていて「もっとフォロワーを増やしたい」「もっと『いいね』が欲しい」と感じることがありますが、これもドーパミンの「もっともっと」の作用なんだと気づかされました。バランスが本当に大切ですね。
「幸せの三段重」と現代社会の変遷
著者は、この「3つの幸福」の理論が、「コロナ禍」によって改めて注目されるべき時が来たと強調しています。
コロナ禍は、私たちに「生き方」「働き方」を見つめ直す機会を与え、「健康」のありがたさ、すなわちセロトニン的幸福の重要性を痛感させました。
また、バブル崩壊は「お金だけでは幸せになれない」というドーパミン的幸福の虚しさを、東日本大震災は「つながり」の尊さ、つまりオキシトシン的幸福の重要性を、日本人に深く認識させるきっかけになったと分析しています。
これらの経験を経て、ようやく「健康→つながり→成功」という「幸せの三段重」の順番で幸福を大切にするという提言が、多くの人々に受け入れられる時代になったと結論付けています。

この部分を読んで、本書が生まれた背景と、なぜ今この理論が重要なのかが明確に理解できました。
まさに、時代がこの「3つの幸福」の概念を求めているのだと感じます。私たちは、過去の経験から多くの教訓を得てきました。
経済的な豊かさだけでは満たされないこと、そして、何かを失って初めてその大切さに気づくこと。
そうした経験を経て、ようやく私たちは「本当の幸せとは何か」という根源的な問いに向き合う準備ができたのだと感じました。
この「幸せの三段重」というフレームワークは、複雑な現代社会を生き抜くための道標になるに違いありません。
本日のまとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、私たちが日々の生活で漠然と感じている「幸せ」について、「セロトニン的幸福(健康)」「オキシトシン的幸福(つながり)」「ドーパミン的幸福(成功)」という3つの視点から掘り下げてみました。
特に重要なのは、この3つの幸福には明確な順番があるという点です。
私たちの心と体の基盤となる「健康」というセロトニン的幸福がしっかりしていれば、安定した人間関係であるオキシトシン的幸福が築かれ、その上で目標達成や自己成長といったドーパミン的幸福が実現しやすくなるのです。
まさに、三段重のように、下の段がしっかりしているからこそ、上の段が安定して積み重なる。
この「幸せの三段重理論」は、私たちがより充実した人生を送るための重要な指針となりそうです。
日々の忙しさに追われ、つい「健康」や「人間関係」を後回しにしてしまいがちですが、このブログが、あなたの「幸せ」を見つめ直すきっかけとなれば幸いです。
まずは、ご自身のセロトニン的幸福から見直してみてはいかがでしょうか。
もし、今回のブログでご紹介した「幸せの三段重」についてもっと深く知りたい方は、書籍『精神科医が見つけた3つの幸福』をぜひ読んでみてくださいね! きっと、あなたの人生を豊かにするヒントが見つかるはずです。

▼本書の詳細・購入はこちら