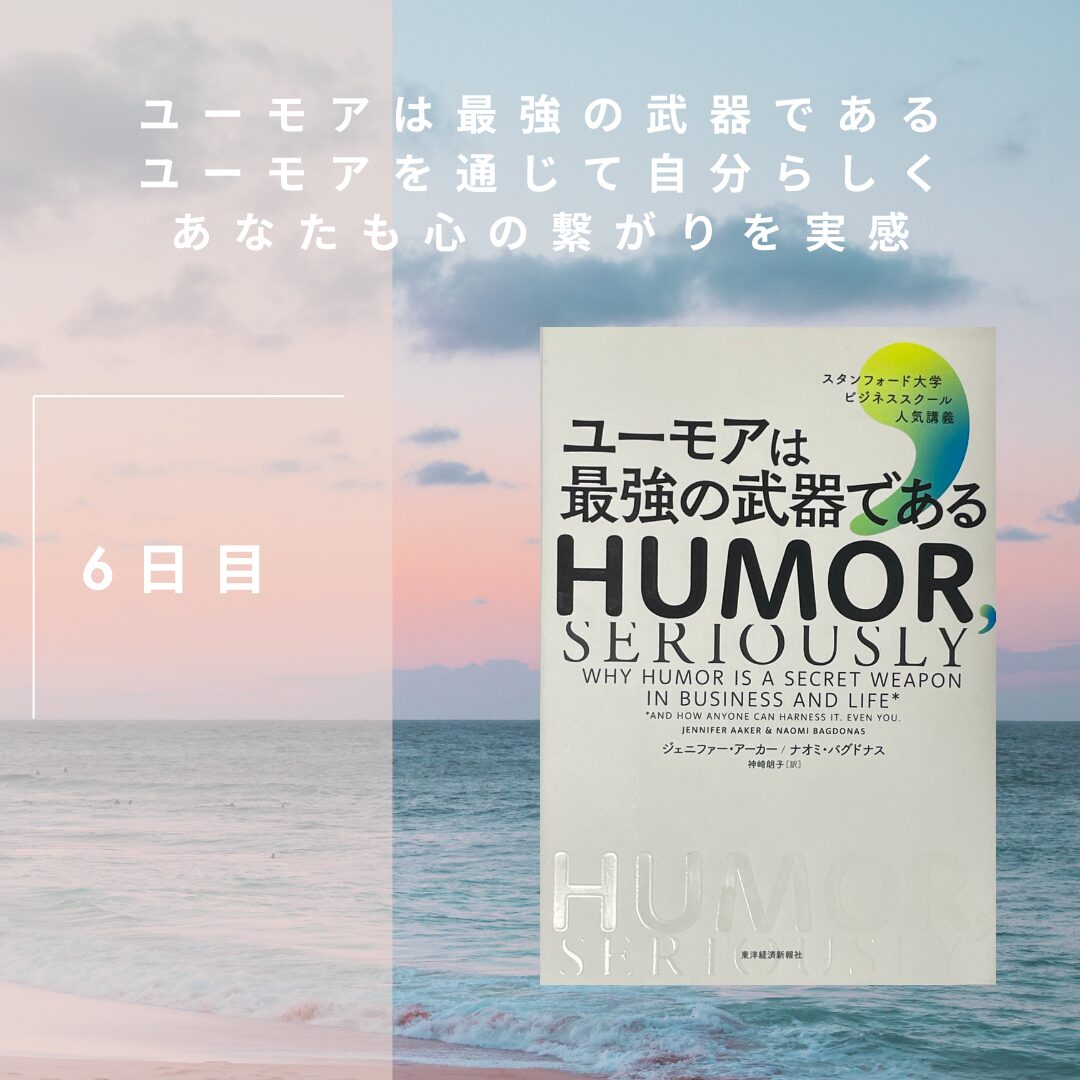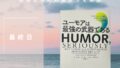著者:ジェニファー・アーカー ナオミ・バグドナスタイトル:ユーモアは最強の武器である

こんな人におすすめ
- 日々の仕事や生活にもっと笑いと遊び心を取り入れたい方
- 人間関係をより深め、心の繋がりを実感したい方
- リーダーシップに新たな風を吹かせる方法を探している方
- ユーモアの効果やその科学的根拠に興味がある方
5分で知識を積み上げ豊かな人生の一歩に繋げていきましょう!
「職場で陽気な文化をつくる」
本章ではユーモアの力がいかに職場文化や業績に良い影響を与えるかが紹介されています。
ピクサーを例に、ユーモアを取り入れた文化、チームでは、チーム内のコミュニケーションがスムーズになり、仲間意識やレジリエンスが強化されるというのです。
チームの明るさが組織全体の成績向上につながることを示した調査結果も取り上げられています。
リーダーシップの観点でも、ユーモアは重要な役割を果たします。
リーダーが自らユーモアを発信することで、メンバーも安心して自由に発言できる環境が生まれるのです。
また、陽気な文化の担い手として「扇動者」「カルチャー・キャリアー」「秘宝」の3タイプの従業員を活用する方法も紹介されています。
組織文化を彩る3つのタイプ
陽気なカルチャーを形成する上で重要な役割を担う従業員は、主に「扇動者」「カルチャー・キャリアー」「秘宝」の3つのタイプに分類できます。
⒈扇動者
既存の枠にとらわれず、常に新しい風を吹き込む存在です。
彼らは現状を打破し、組織に変化をもたらす触媒となります。
⒉カルチャー・キャリアー
組織内で尊敬を集める中心的な存在で、ユーモアのセンスも持ち合わせています。
彼らは人々を繋ぎ、陽気な文化を組織全体に浸透させる役割を担います。
3秘宝
目立たないながらも独自の才能を持つ存在です。
彼らの存在は、組織の多様性を象徴し、意外な形でユーモアを生み出す源泉となります。

リーダーはこのような人材の能力把握をし、彼らの有機的なつながりから生まれる喜びの瞬間を見逃さず、必要なサポートをしたあとは邪魔にならないよう、さっと身を引きことが望ましいです。
首を突っ込みすぎると、創造力、自由な発想の機会を奪ってしまう可能性もあります。
さらに、チーム内で偶発的な「ハプニング」を「伝統」として定着させる工夫が提案されています。
これは、組織の伝統(ルール、しきたり)はトップダウンにより押しつけられて定着させるより、ボトムアップにより生まれた方が受け入れられやすい、というものである。
これらを通じて、従業員が笑いを共有し、創造的な環境が育まれる職場が作られていくのです。
読んでみた感想
この章を読んで感じたのは、「ユーモアは単なる笑いではなく、組織の生産性や人間関係を向上させるための強力なツールであること、職場の成功を左右する重要な要素である」を改めて認識しました。
企業は往々にして「効率性」や「結果」を重視しがちですが、それだけでは従業員のモチベーションや創造力は続きませんよね。
ピクサーの例が示すように、笑いや遊び心がもたらす効果は数字だけでは計り知れないものがあります。
また本章では、「仕込みを感じさせないユーモア」が効果的だという話も紹介されています。
これは、無理に笑いを取ろうとする発言よりも、自然なやりとりの中で生まれる笑いの方が場を和ませる、ということです。

笑いのネタを準備することは問題ではないですが、それを全て披露しようとせず、話の流れに任せることで生まれる笑いの方が印象に残りますよね。
また、リーダーシップの観点でいうと、ここまで何度も紹介されていますがリーダーが笑顔を見せることでチームに安心感を与えるという指摘も重要だと感じました。
リーダーが率先してユーモアを発揮することの重要性や、リーダー自身が遊び心を見せることが、組織文化を変える第一歩になるのです。
組織文化における多様性の重要性は、多くの企業にとって有益な視点になるのではないでしょうか。
本日のまとめ
職場でのユーモアは、単なる気晴らしではありません。それはチームの結束力を強化し、生産性を向上させる重要な要素なのです。本章から得られるポイントは
- リーダーの役割: 自らユーモアを発信して、職場に陽気な雰囲気を醸成する
- 3タイプの従業員活用: 扇動者、カルチャー・キャリアー、秘宝タイプを見極め、彼らを活用する
- 伝統の醸成:あくまでボトムアップによる伝統を重視し、受け入れられやすい伝統が生まれてくるように、サポートに徹する
笑いは強力な武器であり、正しい場面で使うことで職場はもっと楽しく、クリエイティブな場所になります。
あなたの職場にも、ぜひこのユーモアという「最強の武器」を取り入れてみてください。
次回はいよいよこの本の最終回です。
感想を交えて発信していきたいと思います!
5分で人生を豊かに、その一歩を踏み出せるきっかけとなれば嬉しいです!
次回もおたのしみに!ここまでご覧いただきありがとうございました!

▼本書の詳細・購入はこちら